活動事例


09
今回取材に応じてくださったのは、NPO法人活エネルギーアカデミー理事長の山崎昌彦さんです。
─ まずは、団体の概要について、教えてください。
山崎:NPO法人活エネルギーアカデミー(以下、活エネルギーアカデミー)は、岐阜県高山市主催の自然エネルギーセミナーに参加した市民が中心となって2014年に設立した団体です。高山市は、日本一広い市(東京都とほぼ同じ面積)であり、その約93%を森林が占めています。しかし、間伐材は地元でうまく活用されず、木工や建築の材料には外国産材が多く使われています。このような非効率な流れを変えるために、活エネルギーアカデミーは新たに物流システムと循環型経済システムを構築して運営しています。なお、活エネルギーとは、省エネ、創エネ、蓄エネ、ムダとりなどを総称するものです。
─ 山崎さんご自身についても、自己紹介をお願いします。

山崎:私がNPOの活動を始めたのは58歳からでした。それ以前は、経営コンサルタントとして日本全国や東南アジアなどのさまざまな業種の現場に出向き、30年間にわたりトヨタ生産方式の経営改善を指導してきました。その経験から、作業の流れを効率化するために、どのようにサイクル化、ルーティン化するのかと考える習慣が身についています。
木の駅プロジェクトと回収トラックの定期運行
─ 木の駅プロジェクトとは、どのような活動ですか?
山崎:「木の駅」(間伐材集積所)プロジェクトは、素人山主が自分の山から切り出した間伐材や林地残材を買い取り、地域の商店などで使える地域通貨を支払う仕組みです。住民によって自主的に運営されているところが、全国に約80か所あると言われています。私は、このプロジェクトの仕掛け人として知られる丹羽健司さんと出会ったとき、高山でこそ取り組むべきだと思い、「やります」と宣言していました。

2016年、メンバー3人が毎週水曜・木曜の午前中、「ゆい」(互助的な協同労働)によって各自の持ち山の間伐を始めました。赤保木地区から始まった「木の駅」は、現在、市内20か所で展開しています。高山市と協働関係をつくり、市域の東側は水曜日、西側は木曜日に、市のトラックの定期便を、木の駅を結ぶようにルートを決めて走らせています。定期運行の仕組み化によって、市内の山主さんは出荷に合わせて計画的に作業を進められるようになりました。
木の駅プロジェクトでは、始めたときよりも集材量が増えており、近年は間伐材の本数が7,000〜8,000本、CO2削減効果が900t程度となっています。木を伐り出す参加者は定年退職後のシニア層が中心ですが、無理のない範囲で山仕事に励んでいるので、病院に通っているメンバーはいません。
今後は、集める間伐材の目標値を下げようと考えています。量を求めて大量に木材を生産するという考え方ではなく、関係人口を増やしたいからです。
枝葉を生かして間伐材の価値を高める取り組み
─ 木の駅から回収される間伐材などは、どのように活用されていますか?
山崎:製紙用・燃料用のチップに加工されるほか、良質なものは建築用材や家具材として利用されます。
赤保木地区の木の駅には、スギ、ヒノキ、カラマツの間伐材のほか、雑木も運ばれてきます。それらを樹種ごとに分けておき、適当な間伐材や端材から薪を作って販売しています。近年、この地域では薪ストーブの利用者が増えており、相場の半額で購入できるので、リピーターが増えています。また、炭焼き窯もありまして、作った炭は主にバーベキュー用として販売しています。




山崎:薪や炭としてのエネルギー利用のほか、スギ・ヒノキは枝葉を残さずに使っています。
葉っぱは、地元の飛騨産業株式会社(高山市)で、アロマオイルやバイオスティミラント資材として加工されます。枝は福井県の工場に持ち込み、建材用に加工されます。


つまり、経営コンサルタント時代とは真逆のことをやっていることになります。たしかに、収益を重視するならば、枝葉は林内に放置することになるでしょう。しかし、私たちが進めた物流の効率化は、単純に収益性を高めるためではなく、先祖から受け継いだ山林の資源を恵みの森として大事に使わせていただくためのものなのです。

地域通貨を中心とした循環型経済システム
─ 地域通貨にも取り組まれているようですが、どのように回しているのですか?
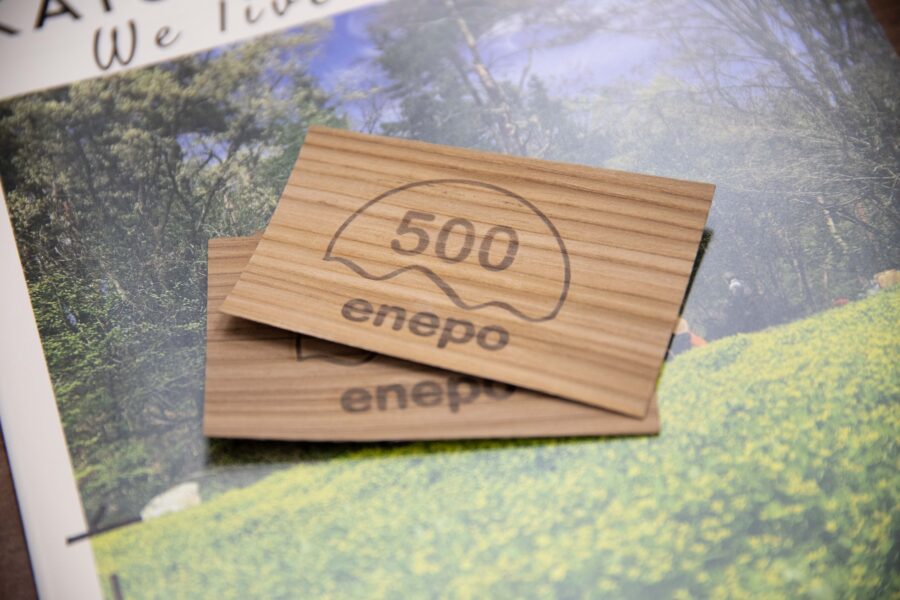
山崎:活エネルギーアカデミーでは、山から搬出した間伐材の売上を元手に、間伐作業や環境活動などの対価として地域通貨「Enepo(エネポ)」を発行しています。Enepoを利用できるお店の数は、最初の7店舗から口コミで広がって現在は約110店舗に増え、利用額は年間480万円を超えています。Enepoは半年に1回、使用期限を設けて発行されており、用途は燃料やアルコール類の購入が多いです。使用された通貨は,地元の飛騨信用組合で現金決済できる協力体制ができています。里山の恵みを地域資源として活用し、さらに地産地消の循環型経済を回す仕組みが、車で15分以内で行ける高山盆地の範囲で実現しています。
全国各地で取り組まれている木の駅プロジェクトは、小学校区ほどの単位で運営されることが多いと聞いています。しかし、活エネルギーアカデミーでは高山市、飛騨産業など地元の木材関連企業、さらに地元の金融機関とも連携して、市全域で取り組んでいます。しかし、そうしたスケールの違いに目を奪われると、地域課題の深さに気づくことができません。
私は62歳から皇學館大学で学び、現在は2つの神社で宮司を務めています。
また、7つの団体で代表を務めています。さらに、地域の製材所に後継者がいないと聞いて、その製材所との連携を考えています。
─ 高山でも人口減少による担い手不足は深刻なんですね。
そうした中で、それほど多くの役割を引き受けているのはどうしてですか?
山崎:それは、目の前に広がる自然の恵みを有効に活かし、地域ぐるみで協力し合うモデルを作ろうとしているためです。また、このような気持ちが沸き起こってくるのは、高山の豊かな森林資源を受け継いできた代々の先祖への感謝と、お互いの良いところも悪いところも見せ合って暮らしていきたいと思える地域の人びとのおかげです。




